重症喘息患者さんの意思決定支援を考える講演会

2025.10.2に行われました重症喘息患者さんの意思決定支援を考える講演会に演者として参加致しました。
講演要旨についてまとめておりますので、ご興味がございましたらごらんください。
重症喘息患者の意思決定支援を本気で考える
講演者:葛西よこやま内科・呼吸器内科クリニック 横山 裕
講演概要
- テーマ:重症喘息治療における意思決定支援(Shared Decision Making: SDM)
- 目的:医療者と患者が共に納得できる治療方針を形成すること
- 対象:最大限の既存治療でも増悪を起こす重症喘息患者
生物学的製剤の目的と課題
- 喘息増悪の抑制、経口ステロイド(OCS)の減量・回避
- QOLおよび呼吸機能の改善、長期的有効性と安全性の確保
- 高額な薬価が治療導入の障壁となる
引用:厚生労働省「医療費助成制度について」(2023)
資料リンク
KOFU Studyの示唆
研究概要:重症喘息患者1,247名を対象としたインターネット調査(Tamada T et al, 2021)
- Bio施行群:29.9%がOCS連用、未施行群では52.1%と高率
- 患者の重症度認識と医師判断に乖離あり
- Bio未施行群は費用負担を重視、施行群は長期的効果を重視
- Bio導入には複数回の説明が必要
文献:Tamada T et al. Therapeutic Research. 2021;42(12):853–860. PubMed
意思決定支援のポイント
- 重症喘息であることを患者に説明
- Bio製剤の効果(症状改善・増悪予防・作用機序)を伝える
- ステロイド使用の将来リスクを説明
- 高額療養費制度など費用軽減策を案内
- OCSを2回使用した段階で早期にBioを紹介
- 看護師・MSWなど多職種で支援
Shared Decision Making(SDM)の重要性
- 患者と医療者が情報を共有し、エビデンスと価値観に基づいて決定するプロセス
- 満足度・アドヒアランスの向上、後悔の減少、転帰の改善
- 低ヘルスリテラシー層にも有効で健康格差の是正につながる
1) Glass KE et al. Patient Educ Couns. 2012;88(1):100–105.
2) Shay AL et al. Med Decis Mak. 2015;35(1):114–131.
3) Zolnierek KB et al. Med Care. 2009;47(8):826–834.
4) Durand MA et al. PLoS One. 2014;9(4):e94670. PubMed
短時間でも実践できるSDM会話法
- 「今の話を聞いてどう感じましたか?」と開かれた質問を行う
- 「納得できる治療を一緒に考えましょう」とパートナーシップを形成
- 医療者の考えを率直に伝え、理解確認を行う
引用:中島俊『こころが動く医療コミュニケーション読本』(医学書院, 2023)
ディシジョンエイドとナッジ理論
- 患者が自宅で情報を整理できるように支援
- 多職種で共有し、質の高い意思決定を促す
- ナッジ理論により行動変容を自然に促す
引用:厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック 明日から使えるナッジ理論」
公式PDF
行動経済学的アプローチ
- 現在バイアス:目先の支出を重視 → 長期的利益を説明
- 現状維持バイアス:変化を避けがち → メリット・デメリットを可視化
- 「皆さん現状維持を選びたがる傾向があります」と前置きして説明
引用:大竹文雄, 平井啓『医療現場の行動経済学』(日本評論社)
高額療養費制度と費用負担
- デュピルマブ3か月処方:自己負担8,000〜10,000円/月(所得区分エ・付加給付あり)
- 指定難病助成によりさらに負担軽減
- 企業健保では付加給付制度あり(2〜3万円超過分を補助)
- 医療費控除も利用可能(確定申告で還付)
ECRS合併と重症喘息
- 成人発症喘息で多く見られ、FeNO高値・嗅覚障害・NSAIDs不耐症を伴う
- デュピルマブが鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(CRSwNP)に有効
- ECRS合併喘息は重症化リスクが高い
Kobayashi Y et al. J Asthma. 2015;52(10):1060–4.
Laidlaw TM et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(3):1133–1141.
Take Home Message
医療者に求められているのは「患者を説得すること」ではなく、 「患者自身が治療方針を決定できるよう支援すること」である。参考文献
- Tamada T et al. Therapeutic Research. 2021;42(12):853–860.
- Glass KE et al. Patient Educ Couns. 2012;88(1):100–105.
- Shay AL et al. Med Decis Mak. 2015;35(1):114–131.
- Zolnierek KB et al. Med Care. 2009;47(8):826–834.
- Durand MA et al. PLoS One. 2014;9(4):e94670.
- Goto Y et al. PLoS One. 2021;16(2):e0247831.
- Matsunaga K et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3(5):759–764.e1.
- Kobayashi Y et al. J Asthma. 2015;52(10):1060–4.
- Laidlaw TM et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(3):1133–1141.
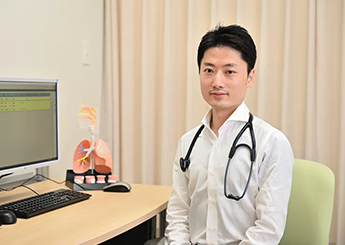
葛西よこやま内科・
呼吸器内科クリニック
院長 横山 裕
医院紹介
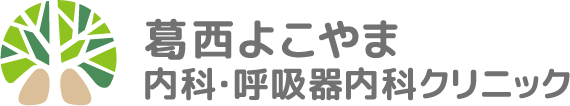
| 住所 | 〒134-0084東京都江戸川区東葛西5丁目1-2 第二吉田ビル3階 |
|---|---|
| 東京メトロ東西線 浦安、西葛西より2分、南行徳より4分、行徳より6分、妙典より8分 |
|
| TEL | 03-3877-1159 |
3階(院長)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |
| 13:30~18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
休診日:木・土(午後)・日・祝日
▲… 8:30〜14:00
※午前の受付は12:00までとなります。
4階(女性医師)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |
| 13:30~16:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
休診日:木・土(午後)・日・祝日
▲… 8:30〜13:00
※午前の受付は12:00までとなります。





