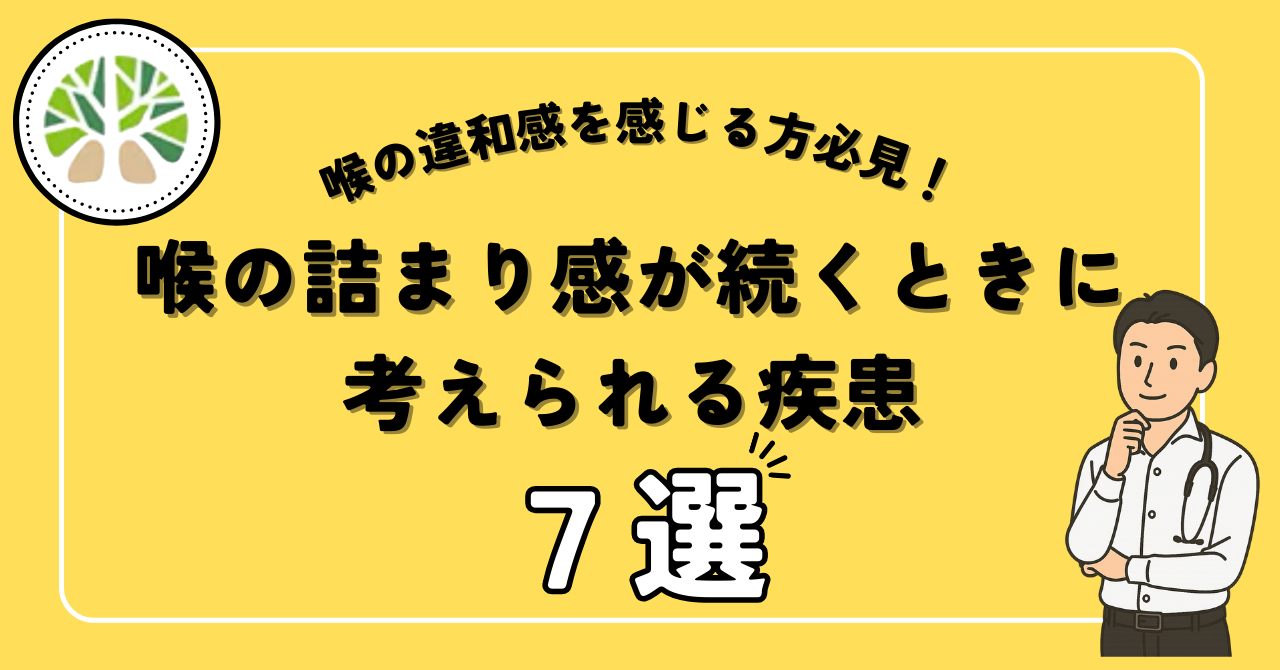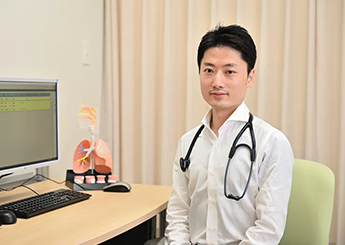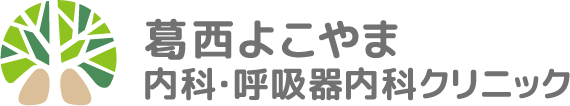喉の違和感・詰まった感じが続くときに考えられる原因

「喉に何かがつまった感じがする」「ヒリヒリ・イガイガが取れない」「痰がひっかかる気がする」—— こうした喉の違和感(咽喉頭異常感)は、見た目では分かりにくい一方で生活の質(QOL)を大きく下げます。 背景には咳喘息や 逆流性食道炎(GERD)、 鼻や副鼻腔の病気、さらにはCOPDなど全身性の疾患も隠れていることがあります。 本記事では症状のチェック→原因→検査→ケース別の見分け方→日常でできる工夫→FAQ→まとめの順に、わかりやすく解説します。
1. こんな症状はありませんか?
咽喉頭異常感は、人によって感じ方がさまざまです。よく寄せられる訴えを挙げます。
-
- 喉がイガイガする
- 喉がヒリヒリ痛むような感覚がある
- 喉に何かがつまった感じがする
- 薄皮が張ったような感覚がある
- 締め付けられるように苦しい
- 常に痰がひっかかっているように感じる
これらは一見「軽い不調」に思えるかもしれませんが、会話や食事、睡眠に影響するなど、日常生活への負担が大きいことも少なくありません。 また、咳や痰を伴う慢性咳嗽の場合もあれば、 違和感だけが続く場合もあります。この「咳・痰の有無」は診断を進める上で重要なポイントになります。
2. 喉の違和感を来す主な原因7選
咽喉頭異常感は一つの病名ではなく、複数の病気が背景にあります。
- アレルギー関連:咳喘息、咽喉頭アレルギー、アトピー咳嗽
- 鼻・副鼻腔:後鼻漏(副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎)
- 胃酸逆流:逆流性食道炎(GERD)、咽喉頭逆流症(LPRD)
- 内分泌・代謝:甲状腺疾患、糖尿病、鉄欠乏性貧血
- 腫瘍:上咽頭がん、食道がん、悪性リンパ腫
- その他:COPD(喫煙関連)、加齢による嚥下障害
- 心因性:ストレス球、心身症、不安神経症、ヒステリー球
3. 当院で可能な検査

原因が幅広いため、症状だけで特定が難しいことがあります。複数の検査を組み合わせて、原因を丁寧に絞り込みます。
- 胸部X線:肺や縦隔の異常をチェック
- 呼気NO検査:喘息やアレルギー性炎症の有無を評価
- 呼吸機能検査/気道抵抗性試験:気道の狭さや過敏性を調べる
- Fスケール:GERDスクリーニング問診票
- RSI:LPRDスクリーニング問診票
- 血液検査:甲状腺・血糖・鉄・膠原病など全身疾患を確認
必要に応じて、上部消化管内視鏡(提携先へ紹介)や、心理検査(ストレス・不安の影響を評価)を追加します。
4. ケース別:症状と考えられる病気
Case 1|アレルギーが関与していそう
夕方〜夜に咳が悪化するが就寝中は咳で起きない。会話中の咳や、季節の変わり目・花粉で悪化する場合はアレルギーが関与している可能性があります。
→ 考えられる病気:咳喘息、季節性喉頭アレルギー、アトピー咳嗽
Case 2|胃酸の逆流が関与していそう
食後や会話中に咳が悪化、胸やけ・もたれ感を伴う場合は胃酸の逆流が疑われます。
→ 考えられる病気:逆流性食道炎(GERD)、咽喉頭逆流症(LPRD)
Case 3|ストレス・心因性が関与していそう
通勤中や仕事中に喉のしめつけ感や空咳が出る一方、休日や就寝中は症状が出にくい場合は心因性の要因が考えられます。
→ 考えられる病気:心因性咳嗽、心身症、ストレス球、声帯機能不全
5. 日常でできる工夫

喉の違和感は、日常生活のちょっとした工夫で軽減できる場合があります。症状が軽い段階では、以下を試してみましょう。
- うがい:こまめなうがいで粘膜を清潔に保ちます。
- 加湿:乾燥は悪化要因です。加湿器や濡れタオルを活用して湿度を保ちましょう。
- 水分摂取:少しずつこまめに水を飲むと喉の粘膜が潤います。
- 刺激物の回避:アルコール、辛い食べ物、炭酸飲料、喫煙は控えると良いでしょう。
- 睡眠時の工夫:逆流性食道炎が疑われる場合は、就寝時に上半身を少し高くして眠ると逆流を防ぎやすくなります。
- 声の使いすぎを避ける:大声や長時間の会話・歌唱は喉に負担をかけます。
ただし、2〜3週間以上続く違和感や、体重減少・血痰・飲み込みにくさを伴う場合は、 単なる生活習慣の問題ではなく病気が隠れている可能性があります。
その際は自己判断せず、早めに医療機関にご相談ください。
6. よくある質問
Q. どのくらい続いたら受診すべき?
2〜3週間以上続く場合や、血痰・体重減少・飲み込みにくさを伴う場合は早めに受診してください。
Q. 市販薬で様子を見ても良い?
加湿・うがい・刺激物回避などで改善することもありますが、長引く・悪化する場合は受診をおすすめします。
7. まとめ|気になる症状は早めに相談を
-
喉の違和感(咽喉頭異常感)は、さまざまな原因で起こることがあります。咳や痰の有無によって診断の進め方が変わるため、丁寧な評価が大切です。
当院では、呼気NO検査や呼吸機能検査、問診票、血液検査などを組み合わせて原因を探っていきます。必要に応じて、耳鼻咽喉科や消化器内科と連携し、より詳しい検査や治療へとつなげていきます。「“ただの違和感”と我慢せず、気になるときは早めにご相談ください。」
👇ご予約・お問い合わせはこちらから👇