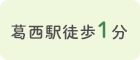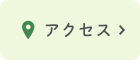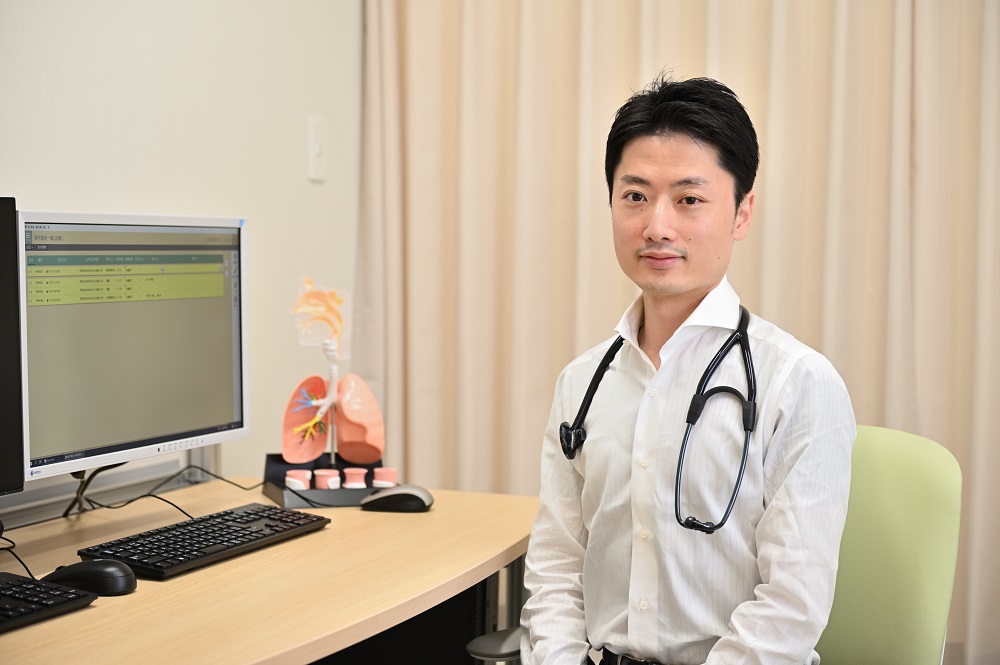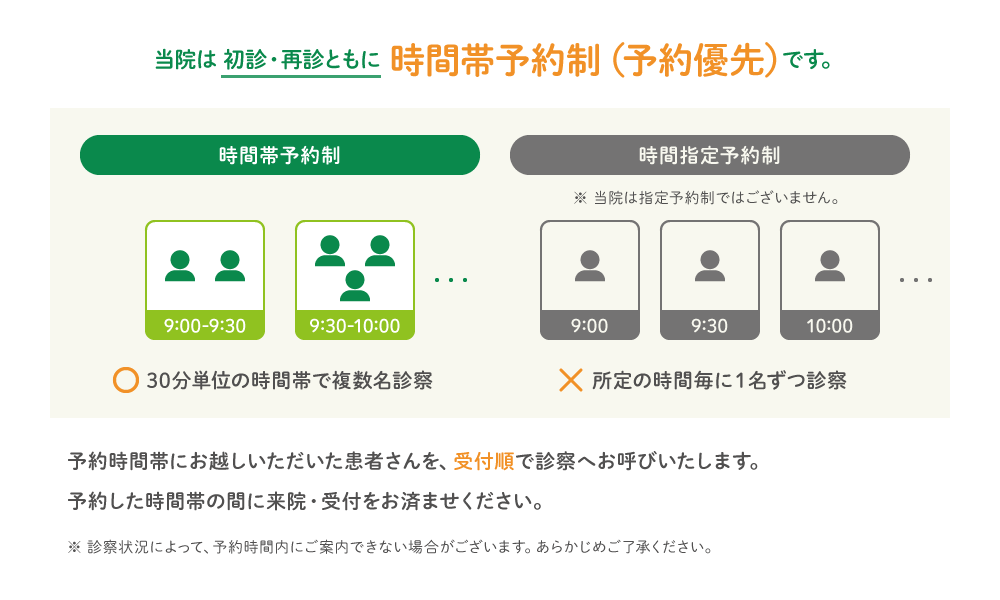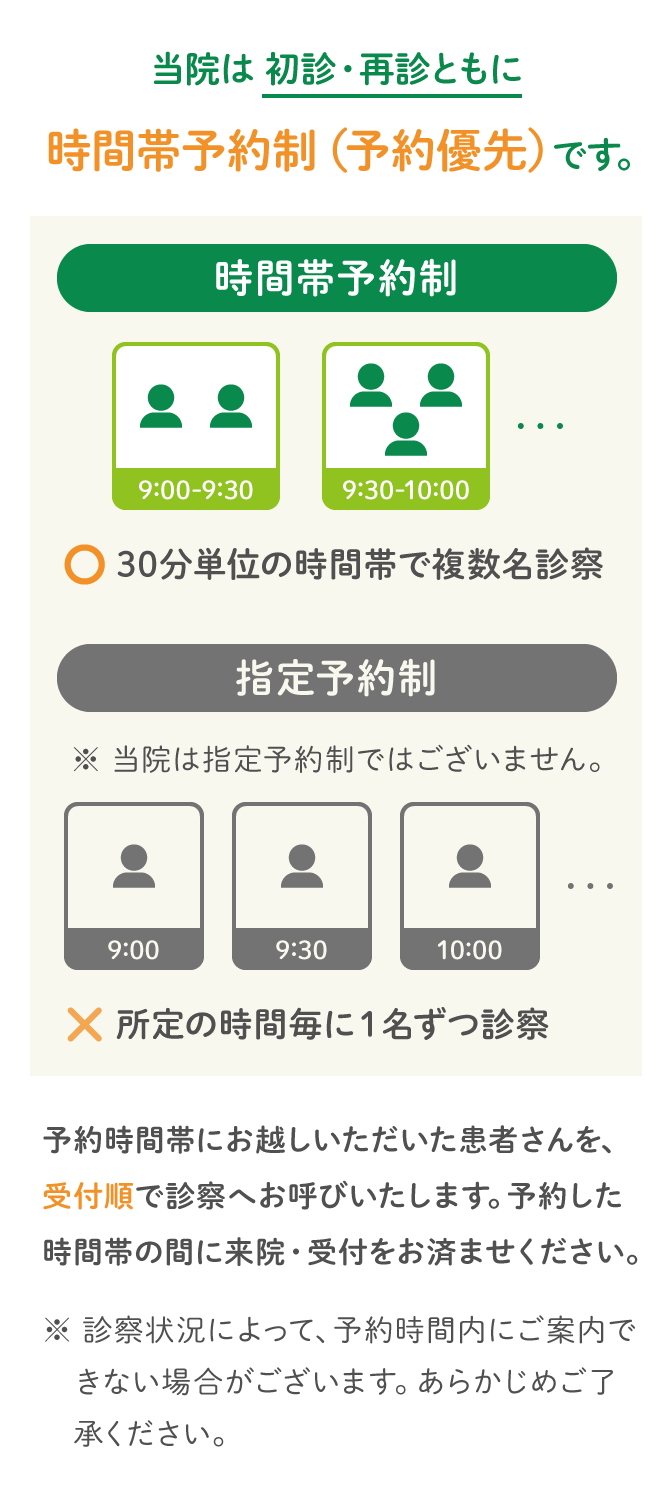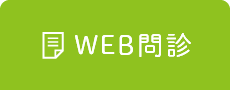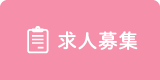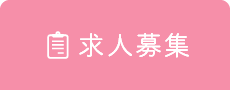会話中に出る咳とは
電話や会議中など会話中に咳が出ることはありませんか?「会話中に咳が出てると相手に心配させてしまう」「咳が出るので電話仕事にならない」など、呼吸器内科の外来には「会話中に出る咳」でお困りの方が多数訪れます。会話中に咳が出るような慢性咳嗽患者さんの多くは「のどのイガイガ感」や、わずかな刺激で咳が誘発されると訴えていることが多く、その誘因としては「香水」や「冷気」「笑い」など日常的な刺激も含まれるということが分かっています(1)。最近の研究では慢性咳嗽が中高年女性に多いという疫学的特徴から「咳嗽受容体の過敏状態(cough hypersensitivity syndrome; CHS)」が疾患概念として提唱されています。このページでは「会話中に出る咳」の原因・検査・治療について解説していきたいと思います。
会話中に出る咳の原因とは
① 咳嗽反射と会話時の生理機序
咳嗽は気道防御の重要な反射であり、気道粘膜の咳受容体が機械的・化学的刺激を受けると迷走神経求心路を介して延髄の咳中枢に信号が伝達されます。中枢からの遠心性経路では反回神経を含む運動神経を介して声帯や呼吸筋が協調的に収縮し、声門の開閉と強制呼気によって咳嗽が生じます。正常ではこの反射が誤嚥防止や異物排出に働きますが、病的に亢進すると微小刺激でも容易に咳が出てしまいます(2)。
② 会話による咳嗽誘発のメカニズム
発声や会話は声帯振動と高速の呼気流を伴うため、喉頭・気道にとって複合的な刺激となり、基礎にある病態次第で咳嗽誘発の誘因となります。
(1)機械的刺激
発声時の声帯振動や気流変動が喉頭・気道粘膜の受容体を物理的に刺激します。喉頭が慢性的に炎症・過敏状態にあると、この軽微な刺激(会話刺激)で反射性に咳嗽が発生します。
(2)乾燥・冷却刺激
長時間話すことで気道粘膜が乾燥・冷却し、気道の温湿度変化に敏感な受容体(鼻や咽頭の温度受容体など)を刺激します。特に気管支喘息や咳喘息など気道過敏性が高い患者では過呼吸や粘膜乾燥により咳嗽が誘発されます。
(3)胃食道逆流の誘発
発声に伴う横隔膜・腹圧の変化で一過性に噴門部がゆるみ、微小な胃内容物の逆流(microaspiration)が起こる場合があります。これにより喉頭や気管が酸刺激を受けたり、食道-気道反射(迷走神経反射)によって咳嗽が引き起こされる可能性があります(3)。正常ではこの反射が誤嚥防止や異物排出に働きますが、病的に亢進するとわずかな刺激でも容易に咳が出てしまいます。
③ 気道過敏性の亢進
会話中に咳が出てしまう原因の1つに「気道過敏性亢進」が挙げられます。「咳喘息」や「気管支喘息」では様々な誘発刺激に対し、気道が過剰に反応し気道が収縮することが知られており、これを「気道過敏性亢進」といいます(4)。気道が収縮した結果、気道平滑筋という筋肉の収縮を介して、咳嗽反射が誘発されます。また「感冒後の状態(感冒後咳嗽)」であっても一時的に「気道過敏性亢進」することも知られています。
・咳喘息
・気管支喘息
・感冒後咳嗽
④ 咳嗽受容体の過敏状態(CHS)
「咳嗽受容体過敏」とは本来咳を起こさない程度の弱い刺激でも咳嗽が誘発される状態を指し、慢性咳嗽患者の共通病態として注目されています(5)。2014年の欧州呼吸器学会(ERS)や2016年の日本呼吸器学会でも「咳嗽受容体過敏症候群(CHS)」が提唱され、原因を問わず8週間以上持続する咳嗽ではこの機序の関与が示唆されています(2)。CHSの臨床像として、香料・冷気・会話などの刺激でのどにむずむずした「咳嗽発作への前触れ」が生じることが特徴であり(1)、これを専門的にはアロタッシー (allotussia) やハイパータッシー (hypertussia) と表現します(5)。例えば、冷空気吸入や香水への暴露で咳き込みや喉の掻痒感が誘発される患者はCHSが示唆されます(1)。CHSは一つの独立疾患ではなく、慢性咳嗽に共通する神経学的なメカニズムであると捉えられています。その背景として、気道知覚神経のニューロパチー(末梢・中枢神経系の変容)の関与が示唆されており(6)(7)、慢性咳嗽患者では延髄孤束核を含む中枢感作や迷走神経系の末梢感作が起こり咳嗽閾値が低下していると考えられています(1)。実際、慢性咳嗽患者の多くでカプサイシン吸入試験*による咳嗽を誘発する閾値が健常者より低下(感受性亢進)しており、治癒に伴い正常化することが報告されています(8)。このような過敏状態はウイルス感染やアレルギー炎症、逆流刺激など様々な要因で誘導され、CHSが持続する限り症状が遷延します。
*カプサイシン吸入試験:
咳嗽受容体の感受性(咳反射閾値)を評価するための検査で、咳嗽受容体過敏症(Cough Hypersensitivity Syndrome, CHS)の評価に用いられる手法。咳嗽の客観的な評価指標として、主に研究目的や難治性咳嗽のメカニズム解析で活用されます。トウガラシ成分であるカプサイシンを溶解し、段階的に吸入させます。どの濃度で咳が何回出るかを計測し、咳反射の閾値(咳を誘発する感受性)を評価する。C2:2回以上の咳を誘発する最小濃度(閾値)、C5:5回以上の咳を誘発する最小濃度(より感受性が高い評価)
会話中に出る咳の原因となる主な病気の特徴と治療
会話中に出る咳の原因となる主な病気の特徴と治療をまとめました。
| 疾患:気管支喘息 病態:アレルギー炎症による「気道過敏性亢進」 症状:咳・痰に加え、喘鳴や呼吸苦を認める 診断:喘息らしさの確認(呼吸機能、呼気NO)、胸部Xpによるその他疾患除外 治療:「吸入ステロイド/β2刺激薬」吸入 |
| 疾患:咳喘息 病態:アレルギー炎症による「気道過敏性亢進」 症状:咳が主体で喘鳴や呼吸苦は認めない 診断:気管支拡張薬(β2刺激薬)が咳嗽に有効、胸部Xpによるその他疾患除外 治療:「吸入ステロイド/β2刺激薬」吸入 |
| 疾患:アトピー咳嗽 病態:中枢気道表層のアレルギーによる咳受容体過敏、多くはアトピー素因を合併 症状:咽喉頭異常感と咳が主体、喘鳴や呼吸苦は認めない 診断:抗ヒスタミン薬が有効、気管支拡張薬は無効、胸部Xpによるその他疾患除外 治療:抗ヒスタミン薬 |
| 疾患:季節性喉頭アレルギー 病態:喉頭のアレルギー炎症による咳嗽、多くは後鼻漏を合併する 症状:咽喉頭異常感と咳が主体、喘鳴や呼吸苦は認めない 診断:抗ヒスタミン薬が有効、気管支拡張薬は無効、胸部Xpによるその他疾患除外 治療:抗ヒスタミン薬 |
| 疾患:咽喉頭逆流症 病態:胃内容物(非酸性や弱酸性のことも)逆流による咽喉頭部の炎症・過敏・刺激 症状:咽喉頭異常感と咳が主体、喘鳴や呼吸苦は認めない 診断:Fスケール問診票、胃内視鏡検査、難治例で24時間インピーダンスモニタリング 治療:制酸剤(PPI)、機能性胃腸薬(イトプリドなど) |
| 疾患:逆流性食道炎 病態:胃内容物逆流による食道逆流、および迷走神経反射による咳嗽 症状:咽喉頭異常感、胸やけを伴う咳が主体、喘鳴や呼吸苦は認めない 診断:Fスケール問診票、胃内視鏡検査、難治例で24時間インピーダンスモニタリング 治療:制酸剤(PPI)、機能性胃腸薬(イトプリドなど) |
| 疾患:感冒後咳嗽 病態:ウイルス感染等による気道粘膜損傷・剥離に伴う一時的な咳過敏状態 症状:感冒症状に引き続き起こる咳や痰、咽喉頭異常感など 診断:先行する感冒症状と、他疾患の除外 治療:対症療法(鎮咳薬など) |
| 疾患:難治性慢性咳嗽 病態:想定される様々な原因に対処したにも関わらず残存する咳嗽、CHSとも関連 症状:各種治療に抵抗性であり長引く咳が主体 診断:慢性咳嗽の原因となる他疾患の除外を行うこと 治療:P2X3受容体拮抗薬(リフヌア)などが一部症例に有効 |
会話中に出る咳の検査
上記疾患を鑑別するために必要な検査をまとめました。一般的にはまず胸部Xpで見逃してはいけない疾患を除外した上で、必要に応じて、呼気NO検査、気道抵抗性試験などで疾患を絞り込んでいきます。
胸部X線:肺炎、見逃してはいけない疾患(肺癌や肺結核など)の除外
副鼻腔X線:副鼻腔炎の診断
呼気NO検査:喘息や咳喘息で上昇する
呼吸機能検査:喘息では気道狭窄がみられる
気道抵抗性試験:咳喘息や喘息で異常となる
アレルギー検査(血液検査):アトピー咳嗽などの診断に有用
まとめ
会話中に出る咳の原因・検査・治療についてまとめました。会話中に出る咳の原因は多岐に渡り、診断するためには詳細な問診や必要な検査を行うことが重要です。咳が長引いて困っている方は、一度呼吸器内科に受診されることをおすすめいたします。
参考:
・のどが原因の咳(季節性喉頭アレルギー、アトピー咳嗽、咽喉頭逆流症)
引用文献:
1.Morice AH, Eur Respir J. 2020 Jan 2;55(1):1901136
2.新実 彰男,日本内科学会雑誌, 2016, 105 巻, 9 号, p. 1565-1577
3.Patel DA,Gastroenterol Hepatol (N Y). 2018 Sep;14(9):512-520
4.井上 博雅, 日本内科学会雑誌, 2006, 95 巻, 8 号, p. 1431-1436
5.Khan D, J Community Hosp Intern Med Perspect. 2024 Nov 2;14(6):75-81
6.Sundar KM, ERJ Open Res. 2021 Mar 29;7(1):00793-2020. doi: 10.1183/23120541.00793-2020
7.Morice AH, et al, Lung 189 : 73―79, 2011.
8.大倉 徳幸, 日本内科学会雑誌, 2020, 109 巻, 10 号, p. 2137-2141,